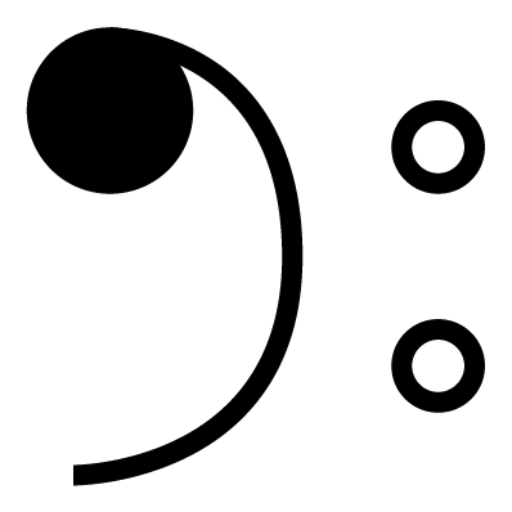
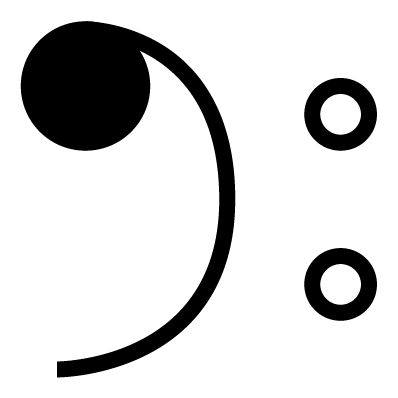
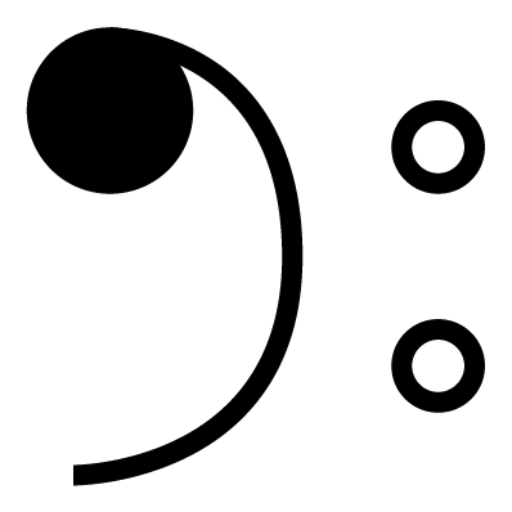
GEN-ON Music of Our Time 2024
Pegasus Concert vol. VI
現音 Music of Our Time 2024
ペガサス・コンサートvol. VI
The Microcosm of The Unaccompanied Contrabass
The Microcosm of The Unaccompanied Contrabass
無伴奏コントラバスの小宇宙
Dec 5th 2024(thu)
19:00 JST (10:00 UTC)
Tokyo Opera City Recital Hall
2024年12月5日(木)19時開演
[:]
P R O G R A M
プログラム
Michio Kitazume : Dance of Gravity(2024)※World Premiere
Daniel D’Adamo : Ombres portées(2017)※Japan Premiere
Brian Ferneyhough : Trittico per G.S.(1989)
Toshi Ichiyanagi : Generation of Space(1985)
Yoshihisa Taira : Convergence II(1976)
Iannis Xenakis : Theraps(1975-76)
Jacob Druckman : Valentine(1969)
北爪道夫 : 重力の舞(2024)※山本昌史委嘱作品・世界初演
ダニエル・ダダモ : Ombres portées(2017)※日本初演
ブライアン・ファーニホウ : Trittico per G.S.(1989)
一柳慧 : 空間の生成(1985)
平義久 : Convergence II(1976)
ヤニス・クセナキス : Theraps(1975-76)
ジェイコブ・ドラックマン : Valentine(1969)
チケット
座席券 ¥3,000
配信視聴券 ¥1,500


Seat 3000JPY / Streaming 1500JPY
◇Ticketing
▼Tokyo Opera City Ticket Center
https://www.operacity.jp/concert/ticket/ticketcenter.php
▼JSCM WEB SHOP
https://jscm.official.ec
Infomation
mail@masashiyamamoto.net
GEN-ON Music of Our Time 2024
Pegasus Concert vol. VI
Masashi Yamamoto 『The Microcosm of The Unaccompanied Contrabass』
Dec 5th 2024(thu) 19:00 JST (10:00 UTC)
Tokyo Opera City Recital Hall
Seat 3000JPY / Streaming 1500JPY
-Program-
Jacob Druckman : Valentine(1969)
Iannis Xenakis : Theraps(1976)
Yoshihisa Taira : Convergence II(1976)
Toshi Ichiyanagi : Generation of Space(1985)
Brian Ferneyhough : Trittico per G.S.(1989)
Daniel D’Adamo : Ombres portées(2017)※Japan Premiere
Michio Kitazume : New Work(2024)※World Premiere
Streaming Ticket
https://jscm.official.ec
問合せ/Infomation
mail@masashiyamamoto.net
The “Pegasus Concert Series” is selected on the basis of outstanding performance skills and expressiveness, creativity and originality of the planning concept and programming, and sufficient cohesiveness as a one-night concert.
優れた演奏技能と表現力を有し、かつ、企画のコンセプトとプログラミングの創造性、独自性の豊かさ、そして、一夜の演奏会としてのまとまりを十分に備えていることを選考基準とする《ペガサス・コンサート・シリーズ》。
Double bassist Masashi Yamamoto has captured contemporary works with an original approach, and with his solid performance technique, he has broken new ground in solo contrabass.
コントラバス奏者・山本昌史は、独創的なアプローチで現代作品をとらえ、確かな演奏技術で独奏コントラバスの新境地を開拓してきた。
This performance will feature masterpieces that draw out the characteristics of the double bass instrument from a variety of perspectives and pursue detailed depictions, unique techniques that take advantage of the double bass's large body and long strings, and masterpieces known to those in the know that are at once outlandish and artistically excellent. No other program is like this one, with an overwhelming presence, including some of the most difficult contemporary solo piece for double bass.
本公演は、さまざまな視点からコントラバスという楽器の特性を引き出し、緻密な描写を追求した傑作、コントラバスの大きな胴体や長い弦を生かした独特な奏法、奇想天外でありながら芸術的にも優れた知る人ぞ知る名作を取り揃える。コントラバス現代作品の中でもとくに難曲と言われる作品をはじめ、圧倒的な存在感を放つこれほどのプログラムは他に類例をみない。
“Trittico per G.S." (Brian Ferneyhough), which requires multi-layered expression with deep insight, and “Convergence II" (Yoshihisa Taira), which carefully confronts inner impulses, have rarely been performed in Japan and will be valuable opportunities.
Also on the program will be “Valentine” (Jacob Druckmann), which has theatrical elements; “Generation of Space” (Toshi Ichiyanagi), which is written in a traditional style that is not too difficult for the instruments; “Theraps” (Iannis Xenakis), which is said to be impossible to perform completely according to the score; and the recently composed “Ombres portees" (Daniel D'Adamo), which was composed in recent years, incorporates all kinds of special techniques of the double bass, and offers a variety of sounds unique to this instrument.
In addition, the world premiere of Michio Kitazume's new piece will be held at the same time as this performance. The birth of a new masterpiece will be the focus of much attention.
深い洞察力で多層的な表現を必要とする『Trittico per G.S.』(B.ファーニホウ)、内なる衝動と入念に向き合う『Convergence Ⅱ』(平義久)、いずれも日本では演奏されることがほとんどなく、貴重な機会となるだろう。
また、演劇的要素をもつ『Valentine』(J.ドラックマン)、伝統的な書法により楽器に無理なく書かれた『空間の生成』(一柳慧)、完全に楽譜通りに演奏することは不可能とも言われる『Theraps』(I.クセナキス)、近年作曲された『Ombres portees』(D.ダダモ)はコントラバスのあらゆる特殊奏法が盛り込まれ、この楽器ならではの多彩な音を聞かせる。
さらに、本公演にて、いよいよ世界初演となる北爪道夫作品。このたび明らかとなったそのタイトル『重力の舞』とは、果たしてどんな作品なのか。新たな名作誕生に期待が高まる。
All of these works create a microcosm that can only be created by the double bass. However, no matter how great the masterpiece, the presence of a player with the appropriate performance technique is indispensable to maximize the interest of the work.
We hope to present “Microcosm of Unaccompanied Double Bass” by Masashi Yamamoto, the one and only double bass player who continues his innovative activities, in a concert that fully expresses the charm of the work with abundant creativity and is worth listening to. Please come and experience an unprecedented double bass solo!
いずれも、コントラバスでしか創り出せない小宇宙を生み出す作品ばかりである。そして、どれほどの傑作であろうとも、作品の醍醐味を最大化する演奏者の存在は欠かせない。
際限なく広がる創造の宇宙を、旺盛な好奇心でひたむきに探求し、唯一無二の革新的な活動を続けるコントラバス奏者・山本昌史による《無伴奏コントラバスの小宇宙》、創意に富んだ作品の魅力を存分に表現し、聞き応えのあるコンサートとなるに違いない。
かつてないコントラバスソロを、是非、ご体感ください!!
一柳慧 : 空間の生成(1985)
重音やハーモニクスを効果的に使用した一聴すると不穏にも感じられる叙情的な導入部から始まる。コントラバスの長い弦長を生かしたグリッサンドを多用しながら音の密度は徐々に濃くなっていき、動きのある中間部に至る。委嘱初演者である溝入氏に作曲家の意図や作品の背景などを伺ったところ、8分音符のフレーズが連続するこの中間部は、一見するとミニマルミュージックのようであるが、無機質に弾いてはならないと一柳氏は言っていたそうである。クライマックスの緊張が解けたあとには、深い余韻とともに静謐な空間が広がる。
初演:1985年6月1日 ルーテル市ヶ谷(東京都新宿区) 溝入敬三
一柳慧(1933-2022)
神戸市に生まれる。若くして渡米し、ジョン・ケージらと実験的な音楽活動を展開した。欧米の前衛音楽を日本に広く紹介し、様々な分野に強い刺激を与える。偶然性や不確定性の音楽、ミニマル・ミュージック、空間性を生かした音楽など、長年に渡り作曲家、演奏家として意欲的に活動し、多くの功績を残した。
ジェイコブ・ドラックマン : Valentine(1969)
1969年に初演されて以来、世界中で最も演奏回数が多いと思われる独奏コントラバスのための現代作品。それまでの「ルール」と「伝統」を破り、作品に演劇的な要素を加えるだけでなく、楽譜を「再発明」した。
五線譜の下にはさらに2本の線が記され、上には声楽用の五線譜が追加されている。音符の符頭は、白、黒、それぞれ、円形、三角形、四角形、×印など、全て異なる奏法を意味する。 拍子やテンポが設定される代わりに、5秒間隔でおおよその経過時間が表示されている。演奏者は、このあまりにも多すぎる楽譜上の情報を読み取り、表現することを要求される。
ジェイコブ・ドラックマン(1928-1996)
アメリカ・コネチカット州に生まれ、15歳で作曲を始める。ジュリアード音楽院、パリのエコールノルマル音楽院で学んだ後、ジュリアード音楽院で教鞭をとった。電子音楽やオーケストラ、小規模アンサンブルのための多くの作品に取り組み、1972年にピューリッツァー賞を受賞。1982〜85年までニューヨークフィルのコンポーザーインレジデンスを務めた。
平義久 : Convergence II(1976)
集合、収束という意味を持つ《Convergence》は独奏楽器のための作品集で、Iはマリンバ、IIIはヴァイオリンのために書かれている。特殊な調弦を用い、開放弦とナチュラルハーモニクスの響きを生かした作品。随所に特殊奏法も見られ、静寂と繊細さが際立つ。左手の押弦点から下駒までを鳴らす通常の演奏と同時に、押弦点から上駒まで指板上を鳴らし、独特の和音を奏でる奏法を用いたのは、この作品が最初かもしれない。西洋のリズムとは異なる不規則な間や和歌の韻律を思わせる音使いに、日本の伝統音楽の影響が感じられる。
初演:1976年3月26日 ロワイヤン国際現代芸術祭(ロワイヤン) フェルナンド・グリロ
平義久(1937-2005)
東京に生まれ、東京藝術大学を卒業後渡仏し、パリ音楽院でアンリ・デュティユー、アンドレ・ジョリヴェ、オリヴィエ・メシアンらに作曲を学ぶ。フランス各地の音楽祭から委嘱を受け、ヨーロッパ内で演奏機会が増えた後、1974年に代表作「クロモフォニー」が日本初演され、日本に広く紹介されることとなった。パリを活動拠点に、ヨーロッパ文化の中に身を置くことで逆に日本文化を再認識し、独特の作風を生み出した。
ダニエル・ダダモ : Ombres portées(2017)※日本初演
ボディが大きくなるほど具体的で堂々としたものになり、その影はよりはっきりと投影される。光が当たる角度によって、照らされた胴体から、より正確な、あるいはより遠くのイメージが浮かび上がる。影は常に不透明で、減色され、近似している。それは最初の投影物の痕跡に過ぎない:共鳴、言い換えれば単純化である。
中断することなく演奏されるこのサイクルを構成する5つの作品は、楽器から浮かび上がると同時に、楽器を照らし出す。
各曲は、ナチュラルハーモニクス、楽器の音の性質、弓や左手のテクニック、グリッサンドの多様性、楽器の自然な慣性と速度、重さと軽さなど、コントラバス独自の特徴と能力に光を当てている。(ダニエル・ダダモ/日本語訳:山本昌史)
初演:2017年2月18日 プレゼンス・フェスティバル(パリ) フロランタン・ジノ
ダニエル・ダダモ(1966-)
ブエノスアイレスに生まれ、そこで音楽家としての訓練を始める。1992年に渡仏、リヨン国立高等音楽院でフィリップ・マヌリに作曲を師事し、IRCAMにてトリスタン・ミュライユとブライアン・ファーニホウに師事した。大編成アンサンブルやモノドラマ、室内オペラなど、作品は北米、南米、アジア、ヨーロッパで演奏され、フランス国内の様々な音楽祭から委嘱を受けている。
ブライアン・ファーニホウ : Trittico per G.S.(1989)
G.S.とは、アメリカの著作家、詩人、美術収集家のガートルード・スタインのことで、タイトルを訳すと《G.S.のための三部作》となる。
独奏曲であるにもかかわらず楽譜は2〜3段に分かれ、ファーニホウの他の作品のように、全ての音素材が複雑に絡み合っている。段ごとに異なるリズムが極度に入り組み、それぞれの音符への指示は微細にわたり、情報量は尋常でない。コントラバスには演奏困難なようにも思える速いパッセージ、跳躍、重音の断片が五線をまたいで即座に切り替わり、しかしそれぞれの五線は独立した意味を保ち続ける。
初演:1990年3月1日 カフェ・ド・ユニ(ロッテルダム)ステファノ・スコダニッビオ
ブライアン・ファーニホウ(1943-)
イギリス・コヴェントリーに生まれる。バーミンガム音楽院を経て、英国王立音楽院で作曲をレノックス・バークリーとハンプリー・サールに師事した。その後アムステルダムにてトン・デ・レーウ、バーゼルにてクラウス・フーバーに作曲を学び、様々な作曲賞を受賞。フライブルク音大、カリフォルニア大学サンディエゴ校で教え、現在はスタンフォード大学で教鞭をとっている。
ヤニス・クセナキス : Theraps(1975-76)
「Crushing the string」の指示から始まり、全体は大まかに、複雑な連符が連続する単旋律、重音のナチュラルハーモニクス、重音のグリッサンドという三つの部分から成る。確率的原理に関連した「ブラウン運動」理論に基づいている。
作曲者と親交のあったフランスのコントラバス奏者ジャン=ピエール・ロベールによると、初版発行時、演奏困難であるとの声を受け、解説付きで第2版が出版された。イギリスのコントラバス奏者バリー・ガイによる奏法解説には、単旋律は指一本で押さえるよう指示があり、ダイナミクスはどれだけ誇張してもよく、指定のテンポは最小限である、と記されている。解説の最後は「セラプスに完全に入り込むには、演奏者は思い切って飛び込む必要がある。なぜなら、クセナキスは演奏者を限界まで、そしてさらにその先へ連れて行くからだ。」と締めくくられる。
初演:1976年3月26日 ロワイヤン国際現代芸術祭(ロワイヤン) フェルナンド・グリロ
ヤニス・クセナキス(1922-2001)
ルーマニア・ブライラに生まれる。10歳の時ギリシャへ向かい、音楽と出会う。アテネ工科大学にて建築と数学を学び、第2次世界大戦中にギリシャ国内で反ナチス・ドイツのレジスタンス運動に加わる。1948年より建築家ル・コルビュジェの弟子となる。建築家として才能を発揮する傍ら、パリ音楽院にてオリヴィエ・メシアンらに作曲を学ぶ。メシアンからの進言により、数学の論理を応用した作曲方法で斬新な作品を生み出した。
北爪道夫 : 重力の舞(2024)※山本昌史委嘱作品・世界初演
映画「ゴジラ」の咆哮はコントラバスの音素材から作られました。一方で、どの弦楽器よりも甘い歌を奏でるこの楽器の、多岐にわたるクオリティの高さに遭遇した私は、「皆さん、もっとコントラバスの近くに集まって!」とお誘いしたいです。
この作品のタイトル『重力の舞』というネーミングは、広く深く大きな表現力をもつコントラバスの「佇まい」から出発しており、演奏者を伴って直立するこの楽器を眺めているだけで私は充分に音楽をしている気になります。舞は曲想に影響を受けたモーションを導入し、また音楽的表現を拡大して見せますが、バレーのような跳躍的傾向は皆無です。地面と周囲の空間を意識した作品として、楽器のエンドピンを軸にしてゆっくり回転できる環境が必要でした。また、インプロヴィゼーションを挿入することにより演奏者のカラーを方向づけることを狙っています。叫びやシラブルの発声は、意味内容ではなく音響的傾向により選ばれました。(北爪道夫)
北爪道夫(1948-)
東京藝大大学院修了。1977〜85年「アンサンブル・ヴァン・ドリアン」の企画作曲指揮で内外の現代作品を紹介、グループで中島健蔵賞受賞。1979年文化庁派遣で渡仏以降、多様な音楽活動を続け、2度の尾高賞、「サントリー芸術財団作曲家の個展」等の成果で中島健蔵賞を再度受賞。またユネスコ作曲家審議会グランプリ、芸術祭大賞、吹奏楽アカデミー賞、クラリネット協会賞等。創作のヒントはまさに森羅万象から得ている。愛知県立芸大名誉教授。

